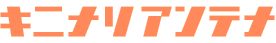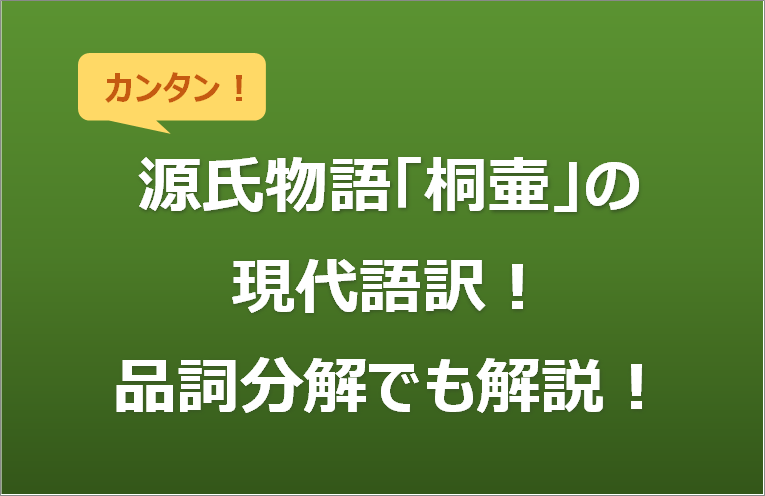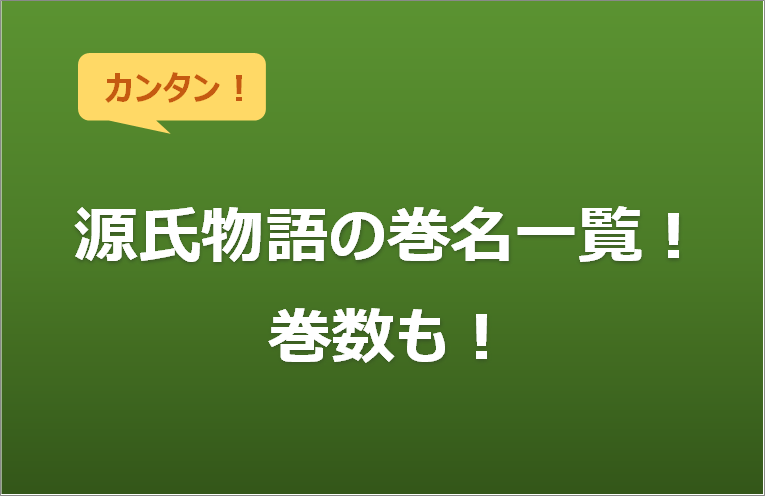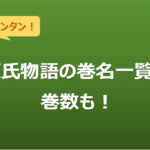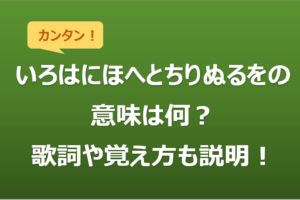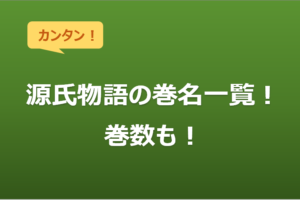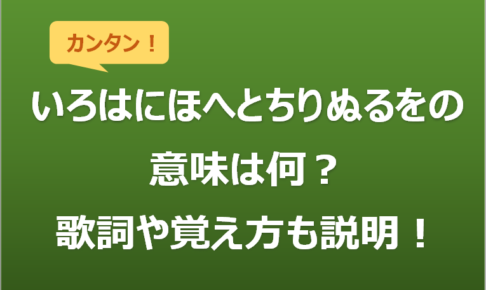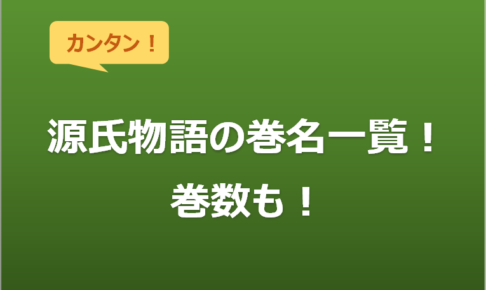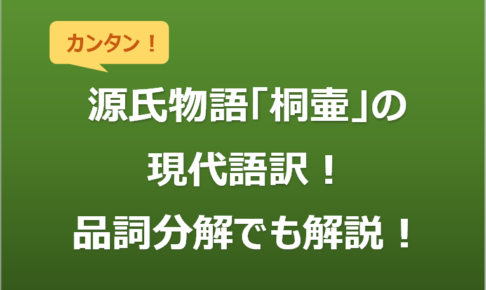源氏物語「桐壷」光源氏の誕生の現代語訳をサクッと把握したいときはないでしょうか。
けど、そんな中で悩むことは、
・源氏物語「桐壷」光源氏の誕生を品詞分解で把握したいがわからない。
ですよね。
今回はそんなお悩みを解決する
・源氏物語「桐壷」光源氏の誕生(いづれの御時にか)の品詞分解
についてまとめます!
もくじ
源氏物語「桐壷」の内容は?
源氏物語「桐壷」は以下の三章の構成となり光源氏誕生前後から成人までの物語となります。
| 第一章 光る源氏前史の物語 | |
| 第一段 父帝と母桐壺更衣の物語 | |
| 第二段 御子誕生(一歳) | |
| 第三段 若宮の御袴着(三歳) | |
| 第四段 母御息所の死去 | |
| 第五段 故御息所の葬送 | |
| 第二章 父帝悲秋の物語 | |
| 第一段 父帝悲しみの日々 | |
| 第二段 靫負命婦の弔問 | |
| 第三段 命婦帰参 | |
| 第三章 光る源氏の物語 | |
| 第一段 若宮参内(四歳) | |
| 第二段 読書始め(七歳) | |
| 第三段 高麗人の観相、源姓賜わる | |
| 第四段 先代の四宮(藤壺)入内 | |
| 第五段 源氏、藤壺を思慕 | |
| 第六段 源氏元服(十二歳) | |
| 第七段 源氏、左大臣家の娘(葵上)と結婚 | |
| 第八段 源氏、成人の後 |
源氏物語の作者や年代は?
源氏物語の作者は紫式部で、平安中期を舞台とした長編小説です。書き始められた年代は1001年ごろとされています。
源氏物語「桐壷」光源氏の誕生の原文と現代語訳
源氏物語「桐壷」光源氏の誕生の原文と現代語訳について説明をします。
いづれの帝の時代であったかよくわからないけど、女御や更衣がたくさん仕えている中に、それほど高貴な身分ではない方であったが、とてもとても帝のご寵愛を受けている方がいました。
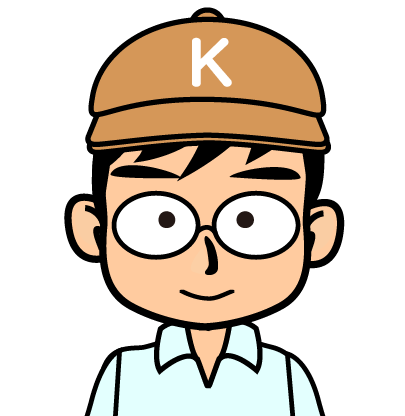
はじめより我はと思ひ上がり給へる御方々、めざましきものにおとしめ 嫉み給ふ。同じほど、それより下臈の更衣たちは、まして安からず。
朝夕の宮仕へにつけても、人の心をのみ動かし、恨みを負ふ積もりにやありけむ、いと篤しくなりゆき、もの心細げに 里がちなるを、いよいよ あかずあはれなるものに思ほして、人のそしりをもえ憚らせ給はず、世のためしにもなりぬべき御もてなしなり。
宮廷に仕え始めた自分こそは帝の寵愛を受けるべき身であると自負している方々は、その女性を気に食わない者としておとしめ妬みます。
その女性と同じ身分、それよりも下の身分の更衣たちは、なおさら心安らかではなかったでしょう。
その女性の朝夕の宮仕えにつけても、周りの人の心を動揺させ、恨みを受け続けたからでしょうか、その女性はたいへん病気がちになり、なんとなく心細そうに里帰りをすることが多くなってきました。
そんな状況を見ていた帝は、ますます限りなく気の毒だと思い、周りの人が悪くいうのも気にしないで、世間の語り草にもなるほど御もてなし、寵愛を続けたそうです。
上達部、上人なども、あいなく目をそばめつつ、いとまばゆき人の御おぼえなり。
唐土にも、かかる事の起こりにこそ、世も乱れ、悪しかりけれと、やうやう天の下にもあぢきなう、人のもてなやみぐさになりて、楊貴妃の例も引き出でつべくなりゆくに、いとはしたなきこと多かれど、かたじけなき御心ばへのたぐひなきを頼みにてまじらひ給ふ。
上達部や上僧人たちが、そんな様子を冷淡な目でみていたけど、まぶしいご寵愛ぶりだったそうです。
唐(中国)でも、このようなことが原因で、世の中が乱れて情勢不安になったけど、次第に世間でもまともでないことと、世間の人々の悩みの種となっていて、楊貴妃の例も引き合いに出してくるような始末なので、寵愛を受けている女性は大変きまりが悪いことが多かったのですが、かたじけないほどの帝の御心を比類なき程強く頼りにして、宮仕えを続けていたそうです。
父の大納言は亡くなりて、
母北の方 なむ古の人の由あるにて、親うち具し、さしあたりて世のおぼえ華やかなる御方々にもいたう劣らず、なにごとの儀式をももてなし給ひけれど、
とりたててはかばかしき後ろ見しなければ、事ある時は、なほ拠り所なく心細げなり。
寵愛を受けている女性の父である大納言は亡くなりました。
母親である奥方は、昔風の人で由緒ある家柄の方であって、両親がそろっていて、今のところ世間の評判が華やかな方々に対して見劣りすることなく、どんな儀式(葬儀)でもやってのけてきたのですが、
取り上げてしっかりとした父の代わりとなる人がいないので、何か事があるときには、やはり頼るあてもなく、心細い様子です。
源氏物語「桐壷」光源氏の誕生の品詞分解
源氏物語「桐壷」の品詞分解について説明をします。
いづれの御時にか【慣用句:どの帝のご治世であったか】
女御【名詞:高位女官】
更衣【名詞:更衣(こうい)】
あまた【副詞:数多く】
候ひ/給ひ/ける【ハ行四段活用動詞「候ふ」連用形+尊敬の補助動詞「給ふ」連用形+過去の助動詞「けり」連体形:お仕えしなさった】
中【名詞:中】
に【格助詞:に】
いと【副詞:それほど】
やむごとなき際【名詞:高い身分】
に【格助詞:に】
は【係助詞:は】
あら/ぬ【ラ行変格活用動詞「あり」未然形+打消の助動詞「ず」連体形:存在しない】
が【格助詞:が】
すぐれ/て【ラ行下二段活用動詞「すぐる」連用形+接続助詞:すぐれて】
時めき/給ふ/あり/けり【カ行四段活用動詞「時めく」連用形+尊敬の補助動詞「給ふ」連体形+ラ行変格活用動詞「あり」連用形+過去の助動詞「けり」終止形:栄えなさるのが存在した】
はじめより【慣用句:最初から】
我【名詞:私】
は【係助詞:は】
と【格助詞:と】
思ひ上がり/給へ/る【ラ行四段活用動詞「思ひ上がる」連用形+尊敬の補助動詞「給ふ」已然形+完了の助動詞「り」連体形:自負しなさっている】
御【接頭語】
方方【名詞:方々】
めざましき【シク活用形容詞「めざまし」連体形:素晴らしい】
もの【名詞:もの】
に【断定の助動詞「なり」連用形:に】
おとしめ【マ行下二段活用動詞「おとしむ」連用形:見下し】
嫉み/給ふ【マ行四段活用動詞「嫉む」連用形+尊敬の補助動詞「給ふ」終止形:ねたみなさる】
同じほど【名詞:同じくらいの身分の人】
それより【不明:それから】
下臈【名詞:身分の低い者】
の【格助詞:の】
更衣【名詞:更衣(こうい)】
たち【接尾語:達】
は【係助詞:は】
まして【副詞:いっそう】
安から/ず【ク活用形容詞「安し」未然形+打消の助動詞「ず」終止形:心穏やかではない】
朝夕【名詞:毎日】
の【格助詞:が】
宮仕へ/に/つけ/て【ハ行下二段活用動詞「宮仕ふ」連用形+完了の助動詞「ぬ」連用形+カ行下二段活用動詞「つく」連用形+接続助詞:いつも奉公していて】
も【係助詞:も】
人【名詞:人】
の【格助詞:の】
心【名詞:心】
を【格助詞:を】
のみ【副助詞:だけ】
動かし、【サ行四段活用動詞「動かす」連用形:動かして、】
恨み【名詞:恨み】
を【格助詞:を】
負ふ【ハ行四段活用動詞「負ふ」連体形:負う】
積もり/に/や/あり/けむ【ラ行四段活用動詞「積もる」連体形+断定の助動詞「なり」連用形+係助詞「や」+ラ行変格活用動詞「あり」連用形+過去推量の助動詞「けむ」連体形:積もるのであろう】
いと【副詞:とても】
篤しく【シク活用形容詞「篤し」連用形:病気が重く】
なりゆき、【カ行四段活用動詞「なりゆく」連用形:なっていって、】
もの【接頭語:なんとなく】
心細げに【ナリ活用形容動詞「心細げなり」連用形:心細い様子に】
里がちなる【ナリ活用形容動詞「里がちなり」連体形:実家に帰っていることが多い】
を【格助詞:を】
いよいよ【副詞:いっそう[ついに]】
あかず/あは/れ【カ行四段動詞「あく」未然形+打消の助動詞「ず」連用形+未然形+受身・尊敬・自発・可能の助動詞「る」連用形:満足しなかっあわれ】
なる【ラ行四段活用動詞「なる」連体形:なる】
もの【名詞:もの】
に【断定の助動詞「なり」連用形:に】
思ほし/て【サ行四段活用動詞「思ほす」連用形+接続助詞:お思いになって】
人【名詞:人】
の【格助詞:の】
そしり【名詞:悪口】
を/も【格助詞+係助詞:さえも】
え/憚ら/せ/給は/ず、【ア行下二段活用動詞「う」連用形+ラ行四段活用動詞「憚る」未然形+使役・尊敬の助動詞「す」連用形+尊敬の補助動詞「給ふ」未然形+打消の助動詞「ず」連用形:える事をためらわせなさらなくって、】
世のためし【名詞:世間話の種】
に【格助詞:に】
も【係助詞:も】
なり/ぬ/べき【ラ行四段活用動詞「なる」連用形+完了の助動詞「ぬ」終止形+推量・意志・勧誘・当然・命令・適当の助動詞「べし」連体形:なってしまうべき】
御【接頭語】
もてなし【名詞:取り扱い】
なり【断定の助動詞「なり」終止形:である】
上達部【名詞:上流階級の人】
上人【名詞:上人(高徳の僧)】
など【副助詞:なんか】
も【係助詞:も】
あいなく【ク活用形容詞「あいなし」連用形:つまらなく】
目をそばめ/つつ【メ行下二段活用動詞「目をそばむ」連用形+接続助詞:目をそらしては】
いと【副詞:とても】
まばゆき【ク活用形容詞「まばゆし」連体形:まばゆい】
人【名詞:人】
の【格助詞:の】
御【接頭語】
おぼえ【名詞:信望】
なり【断定の助動詞「なり」終止形:である】
唐土【名詞:中国】
に【格助詞:に】
も【係助詞:も】
かかる【連体詞:このような】
事【名詞:事】
の【格助詞:が】
起こり【ラ行四段活用動詞「起こる」連用形:起こり】
にこ【名詞:にこ】
そ【名詞:それ】
世【名詞:世間】
も【係助詞:も】
乱れ、【ラ行下二段活用動詞「乱る」連用形:乱れて、】
悪しかり/けれ【シク活用形容詞「悪し」連用形+過去の助動詞「けり」已然形:悪かった】
と【格助詞:と】
やうやう【副詞:次第に】
天の下【名詞:天下】
に【格助詞:に】
も【係助詞:も】
あぢきなう、【ク活用形容詞「あぢきなし」連用形ウ音便:どうしようもなくて、】
人【名詞:人】
の【格助詞:の】
もてなやみぐさ【名詞:悩みの種】
に【格助詞:に】
なり/て【ラ行四段活用動詞「なる」連用形+接続助詞:なって】
楊貴妃【名詞:楊貴妃】
の【格助詞:の】
例【名詞:例】
も【係助詞:も】
引き/出で/つ/べく【カ行四段活用動詞「引く」連用形+ダ行下二段活用動詞「出づ」連用形+完了の助動詞「つ」終止形+推量・意志・勧誘・当然・命令・適当の助動詞「べし」連用形:引きだしてしまうべきで】
なりゆく/に【カ行四段活用動詞「なりゆく」連体形+格助詞:なっていくと】
いとはし【シク活用形容詞「いとはし」終止形:煩わしい】
た【名詞:た】
な【名詞:な】
き/こ【カ行変格活用動詞「く」連用形+カ行変格活用動詞「く」命令形:きてこい】
と【格助詞:と】
多かれ/ど【ク活用形容詞「多し」已然形+接続助詞:多いけれども】
かたじけなき【ク活用形容詞「かたじけなし」連体形:もったいない】
御【接頭語】
心ばへ【名詞:趣向】
の【格助詞:で】
たぐひ【名詞:たぐい】
なき【ク活用形容詞「なし」連体形:ない】
を【格助詞:を】
頼み【名詞:当てにすること】
に/て【格助詞+接続助詞:で】
まじらひ/給ふ【ハ行四段活用動詞「まじらふ」連用形+尊敬の補助動詞「給ふ」終止形:宮仕えしなさる】
父【名詞:父】
の【格助詞:の】
大納言【名詞:大納言】
は【係助詞:は】
亡くなり/て【ラ行四段活用動詞「亡くなる」連用形+接続助詞:亡くなって】
母北の方【名詞:母親にして父親の正妻である女性】
なむ【係助詞】
古【名詞:過去】
の【格助詞:の】
人【名詞:人】
の【格助詞:の】
由【名詞:理由】
ある/に/て【ラ行変格活用動詞「あり」連体形+格助詞「に」+終助詞「て」:いることで】
親【名詞:親】
うち【接頭語】
具し、【サ行変格活用動詞「具す」連用形:そろって、】
さし【サ行四段活用動詞「さす」連用形:さし】
あたり/て【ラ行四段活用動詞「あたる」連用形+接続助詞:あたって】
世【名詞:世間】
の【格助詞:が】
おぼえ【ヤ行下二段活用動詞「おぼゆ」連用形:感じ】
華やかなる【ナリ活用形容動詞「華やかなり」連体形:華やかである】
御方々【名詞:お方たち】
に【格助詞:に】
も【係助詞:も】
いたう【ク活用形容詞「いたし」連用形ウ音便:激しく】
劣ら/ず、【ラ行四段活用動詞「劣る」未然形+打消の助動詞「ず」連用形:劣らなくって、】
なにごと【名詞:どんなこと】
の【格助詞:の】
儀式【名詞:儀式】
を【格助詞:を】
もも【名詞:桃】
て【名詞:手】
なし/給ひ/けれ/ど【サ行四段活用動詞「なす」連用形+尊敬の補助動詞「給ふ」連用形+過去の助動詞「けり」已然形+接続助詞:なしなさったけれども】
とりたて/て【タ行下二段活用動詞「とりたつ」連用形+接続助詞:とりたてて】
はかばかしき【シク活用形容詞「はかばかし」連体形:順調である】
後ろ見【名詞:後見人】
しな【名詞:身分家柄】
けれ/ば【カ行下一段活用動詞「ける」已然形+接続助詞:蹴ると】
事ある時【名詞:大事な時】
は【係助詞:は】
なほ【副詞:やはり】
拠り所【名詞:拠り所】
なく【ク活用形容詞「なし」連用形:なく】
心細げなり【ナリ活用形容動詞「心細げなり」終止形:心細い様子である】
さいごに
いかがでしょうか。
今回は、
・源氏物語「桐壷」の品詞分解
についてまとめました。
また、他にも便利な方法がありますので、よろしければご参照頂ければと思います。